参加しているアマオケでの事 チェロレッスンや日々の練習について・・・
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
新しく宿題になった曲にハマッてます。
schroederの教本の楽譜がないか探したけれど
ありませんでした。
でも、元の(?)楽譜がありました。
Lee 12 Studies for Perfection of Technique, Op.57
こちらの2曲目なのですが
難しい要素が盛りだくさんで、どうやって崩していこうか
色々対策を練っています。
まずは、弓の動きのパターン。
3ページ後半になると、「タリラッタ タリラッタ タリラッタ」
というパターンが出てきます。
ダウンは節約、スラー最後の音(3番目)も軽くして最後の
スタッカートで弓を上手く戻す。
このパターンのその1が重音の入る4弦間の移弦
その2がG~A線間の移弦(A線開放がちょっとムズイ)
その3がラッタ(3,4個目の音)がA線開放になる、という具合に
バリエーション豊富になっています。
それぞれ、ゆっくり丁寧に弾いて練習しますが
重音のパターンも難しいけれど、何故か3番目が弾きにくい。
(D線の時の音が出にくいから弾きにくいのかな・・・)
音程は、最初からかなり高い所まで上って降りてきますが
この降りる時のポジションの感覚(1の指の動く量)を
把握してびしっと動かすと気持ちよく音程がはまるという事に
気づきました。
なんとなくモニョモニョで動かすと、音を引きずって
ポルタメントかかったような気色わるい曲になってしまうので注意が
必要です・・・。(しばらく悩んだ)
同じポジションで弾ける固まりから、次のポジションへ移る
(5段目の3小節あたりから)時は、どの位の移動量があるのか
確認しながら練習。
どうしても弓が上手く使えない所が、4ページの
下から4,3段目の2小節目にある
2音スラー10音スラーのパターンの所。
その前の小節で弓の位置をある程度準備しておいて
最初の2音スラーで多めに弓を使う。。。で良いのかな?!
この曲の次に宿題予定が、同じくLeeの9番目エチュード。
これも少しだけ面白そうなので譜読みしてしまった。
弓を飛ばすには速いテンポが必要なので、まず
左手しっかり、音程正確に練習 となるのだろう。
途中、たくさん移調する所が大変だけれど
こういう攻略感の感じられる曲は大好き!!
と、こんな感じで基礎練にハマッています。
オケの曲、ドボ8でも基礎練みたいな箇所があります。
ドボ8の楽譜
<チェロパート譜にて説明>
2ページD、4ページM、9ページD・E、10ページCODA10小節から
3楽章終わりから2段目のテナー記号の所から重音へ入る所
11ページDの前4小節(同じパターンが数回)、12ページ13小節目
Hから、14ページ頭から。。。
このような箇所は、多分、基礎が身についている人ほど
苦労なくスラスラっと弾けてしまうんだろうな・・・。
音楽を考えるというよりも、正しい音程でかっちり弾く必要が
あるんじゃないかな~。
ということで、地道にコツコツ練習しています。
チェロの基礎練好きな私にとって、ドボ8はかなり面白い!!!
やっぱり、練習すればしただけの手応えが返ってくるんですよね。
焦らずゆっくり正確に。どういう風に弾くのかという目標の音を
頭にきちんと思い描いて、自分の音を客観的に聴けるように。
(聴けないときは録音練習も! そろそろしないと・・・)
そして、サン=サーンスの歌う箇所の甘い音を出すべく
ロングトーンの練習にも頑張っています。
やっぱり弓の持ち方(人差し指~小指の並べ方 私の悪い所は中指薬指の
間があいてしまう)、アップダウンの時の親指の意識の持ち方
などが問題となっています。
親指以外の4本指が綺麗に弓に並んでくれたらなぁ・・・。
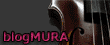

schroederの教本の楽譜がないか探したけれど
ありませんでした。
でも、元の(?)楽譜がありました。
Lee 12 Studies for Perfection of Technique, Op.57
こちらの2曲目なのですが
難しい要素が盛りだくさんで、どうやって崩していこうか
色々対策を練っています。
まずは、弓の動きのパターン。
3ページ後半になると、「タリラッタ タリラッタ タリラッタ」
というパターンが出てきます。
ダウンは節約、スラー最後の音(3番目)も軽くして最後の
スタッカートで弓を上手く戻す。
このパターンのその1が重音の入る4弦間の移弦
その2がG~A線間の移弦(A線開放がちょっとムズイ)
その3がラッタ(3,4個目の音)がA線開放になる、という具合に
バリエーション豊富になっています。
それぞれ、ゆっくり丁寧に弾いて練習しますが
重音のパターンも難しいけれど、何故か3番目が弾きにくい。
(D線の時の音が出にくいから弾きにくいのかな・・・)
音程は、最初からかなり高い所まで上って降りてきますが
この降りる時のポジションの感覚(1の指の動く量)を
把握してびしっと動かすと気持ちよく音程がはまるという事に
気づきました。
なんとなくモニョモニョで動かすと、音を引きずって
ポルタメントかかったような気色わるい曲になってしまうので注意が
必要です・・・。(しばらく悩んだ)
同じポジションで弾ける固まりから、次のポジションへ移る
(5段目の3小節あたりから)時は、どの位の移動量があるのか
確認しながら練習。
どうしても弓が上手く使えない所が、4ページの
下から4,3段目の2小節目にある
2音スラー10音スラーのパターンの所。
その前の小節で弓の位置をある程度準備しておいて
最初の2音スラーで多めに弓を使う。。。で良いのかな?!
この曲の次に宿題予定が、同じくLeeの9番目エチュード。
これも少しだけ面白そうなので譜読みしてしまった。
弓を飛ばすには速いテンポが必要なので、まず
左手しっかり、音程正確に練習 となるのだろう。
途中、たくさん移調する所が大変だけれど
こういう攻略感の感じられる曲は大好き!!
と、こんな感じで基礎練にハマッています。
オケの曲、ドボ8でも基礎練みたいな箇所があります。
ドボ8の楽譜
<チェロパート譜にて説明>
2ページD、4ページM、9ページD・E、10ページCODA10小節から
3楽章終わりから2段目のテナー記号の所から重音へ入る所
11ページDの前4小節(同じパターンが数回)、12ページ13小節目
Hから、14ページ頭から。。。
このような箇所は、多分、基礎が身についている人ほど
苦労なくスラスラっと弾けてしまうんだろうな・・・。
音楽を考えるというよりも、正しい音程でかっちり弾く必要が
あるんじゃないかな~。
ということで、地道にコツコツ練習しています。
チェロの基礎練好きな私にとって、ドボ8はかなり面白い!!!
やっぱり、練習すればしただけの手応えが返ってくるんですよね。
焦らずゆっくり正確に。どういう風に弾くのかという目標の音を
頭にきちんと思い描いて、自分の音を客観的に聴けるように。
(聴けないときは録音練習も! そろそろしないと・・・)
そして、サン=サーンスの歌う箇所の甘い音を出すべく
ロングトーンの練習にも頑張っています。
やっぱり弓の持ち方(人差し指~小指の並べ方 私の悪い所は中指薬指の
間があいてしまう)、アップダウンの時の親指の意識の持ち方
などが問題となっています。
親指以外の4本指が綺麗に弓に並んでくれたらなぁ・・・。
PR
この記事にコメントする
ドボ8
こんにちは。はじめまして。
私は去年ドボ8がオーケストラデビューでした。1楽章D、M、苦労しました!「基礎練」というか「機械になったつもりで」弾こうとがんばりました。1楽章と4楽章冒頭のメロディを弾かせてもらえるお返しだからと思って。がんばってくださいね。
それとScheroederも同じようなところをやっておられますね!私は次は88番が宿題です。親近感を感じて思わずコメントしてしまいました。どうぞよろしく。
私は去年ドボ8がオーケストラデビューでした。1楽章D、M、苦労しました!「基礎練」というか「機械になったつもりで」弾こうとがんばりました。1楽章と4楽章冒頭のメロディを弾かせてもらえるお返しだからと思って。がんばってくださいね。
それとScheroederも同じようなところをやっておられますね!私は次は88番が宿題です。親近感を感じて思わずコメントしてしまいました。どうぞよろしく。
コメント
ありがとうございます!
D,Mの3連符は何も考えなくても自動演奏出来る位に
かっちり練習しないと怖いですね・・・。
私もガンバリマス!!
メロディーを堪能する所もたくさんあるのも勿論
1楽章Bのようなハーモニーが楽しめる所もあるし、
ドボ8は本当に色々な要素が入っていて面白いですね。
自分の役割についても、色々考えさせられます。
yoshiさんもschroeder使われているんですね。
私は難易度低い曲から番号飛び飛びで宿題になっているので
88番みたいな目眩がする曲は…。^^;
でも、この教本は面白くてかなりツボです。
弾きたい曲が弾けるようになる為に、コツコツ頑張っています。
こちらこそ、宜しくお願いします。
次回定演、田園なんですね。
2年ほど前の定演でやりました。
古典苦手だとか、ベートーヴェンらしくってどうなんだ?とか
悩みまくっていたのを思い出します。
今でもベートーヴェンは苦手です。
D,Mの3連符は何も考えなくても自動演奏出来る位に
かっちり練習しないと怖いですね・・・。
私もガンバリマス!!
メロディーを堪能する所もたくさんあるのも勿論
1楽章Bのようなハーモニーが楽しめる所もあるし、
ドボ8は本当に色々な要素が入っていて面白いですね。
自分の役割についても、色々考えさせられます。
yoshiさんもschroeder使われているんですね。
私は難易度低い曲から番号飛び飛びで宿題になっているので
88番みたいな目眩がする曲は…。^^;
でも、この教本は面白くてかなりツボです。
弾きたい曲が弾けるようになる為に、コツコツ頑張っています。
こちらこそ、宜しくお願いします。
次回定演、田園なんですね。
2年ほど前の定演でやりました。
古典苦手だとか、ベートーヴェンらしくってどうなんだ?とか
悩みまくっていたのを思い出します。
今でもベートーヴェンは苦手です。

