参加しているアマオケでの事 チェロレッスンや日々の練習について・・・
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
本日チェロレッスンでした。
 バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエットⅠ、Ⅱ
バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエットⅠ、Ⅱ
 バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 ジーグ
バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 ジーグ
 ブラームス チェロソナタNo.1 1楽章
ブラームス チェロソナタNo.1 1楽章
今日はバッハの新曲を2つ。
メヌエット1は重音がメチャメチャ難しいです・・・。
くり返しを抜けた所のAEを4指で押さえているのですが
とにかく押さえ切れていません。
押さえる時の弦の当たる指の位置など色々試しても出ません。
音が鳴りきらないし、音程もEに合わせるとAの音が高くなります。
4指はA線をしっかり押さえ、D線の方は弦を指板まで押さえこまず
3指はD線を押さえ、そして弓速を速く弾いてみる。
『あ、これだ』というのがあるにはあったのですが
それを見つけるのにまだ異常に時間がかかります。
さっと押さえられるように修行あるのみ。
この部分の練習をしていたら小指が痛くなりました。
久しぶりに関節がコキっとなって戻らなくなりました。
鍛えなくては!!
メヌエット2は柔らかい音で、と思っていたのですが
自分が考えていたよりもしっかり弾かないといけませんでした。
2小節目のA-Fis-Aも1音ずつしっかり良い音で。
3,4小節目はしっかり。(ここがふにゃふにゃすぎた)
この感じを意識するだけでメヌエット2はかなり
音楽になってきた手応えです。
そしてメヌエット1に戻ります・・・ツライ。
和音をゆっくり丁寧に練習すること。
4指で重音を押さえるところ、2指でも考えられるけれど
・・・でも4指で出せるように頑張ってみます!!!
そしてジーグ。
3/8拍子の音楽のパターンはベト1の3楽章にも応用出来る!
という事で、どういう風に音を運んでいくかを考えます。
3拍から1拍へ音が進むのを意識、音と音の間には間(ま)があく。
重音で八分音符、十六分音符を弾くところは正三角形の3拍子。
ワルツのリズムになるとジーグにならないので注意。
曲の最後の処理、揺らすかどうか・・・。
今回は揺らさず弾ききる方向で演奏してみる事にしました。
メヌエットで凹みますが、ジーグは楽しい♪
また次回まで両方とも宿題です。
指の強化、もっと弾き込んで左手がまだ慣れていない箇所を
しっかり練習しておきます。
そしてブラームスのソナタ。
テンポがキープ出来ていない箇所、もっともっと歯を食いしばって
顔を真っ赤にして、お腹に力を入れて我武者羅に
音を出していかなくてはいけない箇所、楽譜のpやdim.に
惑わされてはいけない箇所、ヴィブラートを1音1音かけていく箇所
音程が当たらない箇所、音の重さを感じる箇所、シンコペーションの
リズムを感じる箇所、休符の間に先に左手を用意しておく事
(ヴィブラートをかけて待っている)などなど・・・まだたくさん
注意しなくてはいけない事があります。
音を音楽にするには、音の羅列を意味のあるものに
していく事が必要なんだとわかりました。
次の音へ繋がっていくエネルギー、向かっていく頂点を見極め
そして音の強弱や音色の強さにも関係してくるでしょうか。
同じ音形のくり返しや、最後はGisが3つ並んでいますが
こういう所で音楽を作る作業が必要になってきます。
今オケでブラ1を弾いていますが、同じ事なのだそうです。
こういう作業をしていかないと、ブラームスにならない。
ベートーヴェンも同じで、ブラームスよりも明解な作りになっている
というだけで、同じように音楽を作らなくてはいけない。
具体的に、どういう風に音を弾いていくべきなのか
しっかり楽譜を『読んで』いかないと駄目なのだな、とわかりました。
発表会までレッスンはあと1回。
通して弾いても、左手も右手も多分最後まで力尽きず持つと思います。
後はテンションを保つ事、ピアノを聴く事、慌てない事、かな。
ピアノ合わせはまだ未定ですがピアノ譜も勉強しておかなくちゃ!!!
そして、来年の発表会の曲まで決めちゃいました・・・。
フランス(フォーレ)→ドイツ(ブラームス) ときて
またフランスを弾く予定ですー。楽しみです♪
↓ぽちっと応援してもらえると嬉しいです♪
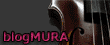

 バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエットⅠ、Ⅱ
バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエットⅠ、Ⅱ バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 ジーグ
バッハ 無伴奏チェロ組曲No.2 ジーグ ブラームス チェロソナタNo.1 1楽章
ブラームス チェロソナタNo.1 1楽章今日はバッハの新曲を2つ。
メヌエット1は重音がメチャメチャ難しいです・・・。
くり返しを抜けた所のAEを4指で押さえているのですが
とにかく押さえ切れていません。
押さえる時の弦の当たる指の位置など色々試しても出ません。
音が鳴りきらないし、音程もEに合わせるとAの音が高くなります。
4指はA線をしっかり押さえ、D線の方は弦を指板まで押さえこまず
3指はD線を押さえ、そして弓速を速く弾いてみる。
『あ、これだ』というのがあるにはあったのですが
それを見つけるのにまだ異常に時間がかかります。
さっと押さえられるように修行あるのみ。
この部分の練習をしていたら小指が痛くなりました。
久しぶりに関節がコキっとなって戻らなくなりました。
鍛えなくては!!
メヌエット2は柔らかい音で、と思っていたのですが
自分が考えていたよりもしっかり弾かないといけませんでした。
2小節目のA-Fis-Aも1音ずつしっかり良い音で。
3,4小節目はしっかり。(ここがふにゃふにゃすぎた)
この感じを意識するだけでメヌエット2はかなり
音楽になってきた手応えです。
そしてメヌエット1に戻ります・・・ツライ。
和音をゆっくり丁寧に練習すること。
4指で重音を押さえるところ、2指でも考えられるけれど
・・・でも4指で出せるように頑張ってみます!!!
そしてジーグ。
3/8拍子の音楽のパターンはベト1の3楽章にも応用出来る!
という事で、どういう風に音を運んでいくかを考えます。
3拍から1拍へ音が進むのを意識、音と音の間には間(ま)があく。
重音で八分音符、十六分音符を弾くところは正三角形の3拍子。
ワルツのリズムになるとジーグにならないので注意。
曲の最後の処理、揺らすかどうか・・・。
今回は揺らさず弾ききる方向で演奏してみる事にしました。
メヌエットで凹みますが、ジーグは楽しい♪
また次回まで両方とも宿題です。
指の強化、もっと弾き込んで左手がまだ慣れていない箇所を
しっかり練習しておきます。
そしてブラームスのソナタ。
テンポがキープ出来ていない箇所、もっともっと歯を食いしばって
顔を真っ赤にして、お腹に力を入れて我武者羅に
音を出していかなくてはいけない箇所、楽譜のpやdim.に
惑わされてはいけない箇所、ヴィブラートを1音1音かけていく箇所
音程が当たらない箇所、音の重さを感じる箇所、シンコペーションの
リズムを感じる箇所、休符の間に先に左手を用意しておく事
(ヴィブラートをかけて待っている)などなど・・・まだたくさん
注意しなくてはいけない事があります。
音を音楽にするには、音の羅列を意味のあるものに
していく事が必要なんだとわかりました。
次の音へ繋がっていくエネルギー、向かっていく頂点を見極め
そして音の強弱や音色の強さにも関係してくるでしょうか。
同じ音形のくり返しや、最後はGisが3つ並んでいますが
こういう所で音楽を作る作業が必要になってきます。
今オケでブラ1を弾いていますが、同じ事なのだそうです。
こういう作業をしていかないと、ブラームスにならない。
ベートーヴェンも同じで、ブラームスよりも明解な作りになっている
というだけで、同じように音楽を作らなくてはいけない。
具体的に、どういう風に音を弾いていくべきなのか
しっかり楽譜を『読んで』いかないと駄目なのだな、とわかりました。
発表会までレッスンはあと1回。
通して弾いても、左手も右手も多分最後まで力尽きず持つと思います。
後はテンションを保つ事、ピアノを聴く事、慌てない事、かな。
ピアノ合わせはまだ未定ですがピアノ譜も勉強しておかなくちゃ!!!
そして、来年の発表会の曲まで決めちゃいました・・・。

フランス(フォーレ)→ドイツ(ブラームス) ときて
またフランスを弾く予定ですー。楽しみです♪
↓ぽちっと応援してもらえると嬉しいです♪
PR

