参加しているアマオケでの事 チェロレッスンや日々の練習について・・・
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日(昨日?)は発表会後の初チェロレッスンでした。
 schroeder 170foundation studiesから 100番 83番
schroeder 170foundation studiesから 100番 83番
 バッハ無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエット1、2 ジーグ
バッハ無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエット1、2 ジーグ
 サン=サーンス チェロ協奏曲 1番
サン=サーンス チェロ協奏曲 1番
久しぶりの練習曲、燃えました!
100番は13小節の左手の動きを確認。
この辺はレガートでリズムが流れてしまっていたので
動きの確認をした時位の確実な慌てないテンポで。
25小節、34小節から5音分の弓量を
スタッカートで調整するようになりますが、ここの弾き方の確認。
100番上がりました。
83番はテヌート気味というかベタベタ弾くというか、そういう感じで。
27小節、ナチュラルが2拍目についているのを4拍目の固まりで忘れて
Fisで弾いてました・・・。
pを弾く時は、弓中の方で。
音がまだ硬いので、弓の持ち方を少々変更。
右手中指をスティックに巻くように持っていたのですが
これを伸ばして弓の毛を触るような感じに。
試しにこの持ち方で弾いてみると、柔らかく音が出せます。
しばらくはこの持ち方でやってみます。
83番も上がりました。この曲は楽しかった!!
次は86番・・・これは凄く凄く難しいです。
音を読むのでまだ精一杯。48小節とか難しいし。。。でもガンバリマス!
続いてバッハ。
メヌエット1番は、最初の重音をDF-FAでしっかり分けて弾く。
重音の時に右手で音を硬くしない。
12小節の所できちんと響いた音で弾く練習をしました。
音が飛んだ時に左手がへこたれずしっかり弦を押さえて
良い音が出せるようにしないといけないんだ・・・。
和音を押さえにいく指がままならなかったり、次へ次へと
焦ってしまったりするので、もっと落ち着かなくては。
慌てて端折るよりはきちんと用意して少し時間が伸びてしまう位の
感覚で、私の演奏はちょうど良いようです。
メヌエット2番で必要音色は、圧力のかかった音ではなく
柔らかい音。
拡張の動きから基本に戻してヴィブラート、など
左手の動きを確認。
メヌエットはもう少し弾き込みます。
・・・というか、もっときちんと弾けないと駄目です。
重音をもっと楽に弾けるようにならないと!!!
ジーグは3→12 という拍の意識を持って演奏する。
拍頭に重音が来るパターンは、その重音の音をしっかり鳴らす。
後半、3音ずつスラーがかかっている所はこのスラーを生かす。
2拍子まではいかないけれど、ニュアンスを。
フレーズ最後の音をしっかり弾くところ、拍の頭をしっかり鳴らすところなど
大体イメージ通りなので、それをきちんと音楽に表せるようにしなくては。
この曲は重く速く。
ということで、テンポもう少し速く、宿題です。
サン=サーンスのチェロコン。
指使いが難しい所(わざとそうしているのだとわかるのだけれど)が
たくさんあるので、先生の指使いを教わる。
先生の楽譜で弾いてみると、かなり違う箇所がありました。
とりあえず1楽章最後まで辿り着きました。
この曲は本当に楽しいです。
ブラームスの後なので、余計開放感があるのかも知れません。
まずは音を正しく並べて正確に弾けるように
そして、音楽をどういう風に作っていくか考えて
テンポを上げていく。 というような目標を立ててみました。
重音のところが大変だけれど、なんとか攻略してみせるぞ~~。
あ、それからチェロオケの本番が近づいてきているのですが
演奏するホルベルク組曲で、3soloがありその部分の
低音を担当する事になったのですが、これがまた
地味に嫌な感じです。
私の音程が全て・・・なのでガンバリマス。
10月、11月に本番各1、12月に2つ。
12月は第九とベト1とブラ1という超豪華な曲ばかり。
大丈夫なんだろうかワタシ・・・。
↓ぽちっと応援してもらえると嬉しいです♪
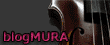

 schroeder 170foundation studiesから 100番 83番
schroeder 170foundation studiesから 100番 83番 バッハ無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエット1、2 ジーグ
バッハ無伴奏チェロ組曲No.2 メヌエット1、2 ジーグ サン=サーンス チェロ協奏曲 1番
サン=サーンス チェロ協奏曲 1番久しぶりの練習曲、燃えました!
100番は13小節の左手の動きを確認。
この辺はレガートでリズムが流れてしまっていたので
動きの確認をした時位の確実な慌てないテンポで。
25小節、34小節から5音分の弓量を
スタッカートで調整するようになりますが、ここの弾き方の確認。
100番上がりました。
83番はテヌート気味というかベタベタ弾くというか、そういう感じで。

27小節、ナチュラルが2拍目についているのを4拍目の固まりで忘れて
Fisで弾いてました・・・。
pを弾く時は、弓中の方で。
音がまだ硬いので、弓の持ち方を少々変更。
右手中指をスティックに巻くように持っていたのですが
これを伸ばして弓の毛を触るような感じに。
試しにこの持ち方で弾いてみると、柔らかく音が出せます。
しばらくはこの持ち方でやってみます。
83番も上がりました。この曲は楽しかった!!
次は86番・・・これは凄く凄く難しいです。
音を読むのでまだ精一杯。48小節とか難しいし。。。でもガンバリマス!
続いてバッハ。
メヌエット1番は、最初の重音をDF-FAでしっかり分けて弾く。
重音の時に右手で音を硬くしない。
12小節の所できちんと響いた音で弾く練習をしました。
音が飛んだ時に左手がへこたれずしっかり弦を押さえて
良い音が出せるようにしないといけないんだ・・・。
和音を押さえにいく指がままならなかったり、次へ次へと
焦ってしまったりするので、もっと落ち着かなくては。
慌てて端折るよりはきちんと用意して少し時間が伸びてしまう位の
感覚で、私の演奏はちょうど良いようです。
メヌエット2番で必要音色は、圧力のかかった音ではなく
柔らかい音。
拡張の動きから基本に戻してヴィブラート、など
左手の動きを確認。
メヌエットはもう少し弾き込みます。
・・・というか、もっときちんと弾けないと駄目です。
重音をもっと楽に弾けるようにならないと!!!
ジーグは3→12 という拍の意識を持って演奏する。
拍頭に重音が来るパターンは、その重音の音をしっかり鳴らす。
後半、3音ずつスラーがかかっている所はこのスラーを生かす。
2拍子まではいかないけれど、ニュアンスを。
フレーズ最後の音をしっかり弾くところ、拍の頭をしっかり鳴らすところなど
大体イメージ通りなので、それをきちんと音楽に表せるようにしなくては。
この曲は重く速く。
ということで、テンポもう少し速く、宿題です。
サン=サーンスのチェロコン。
指使いが難しい所(わざとそうしているのだとわかるのだけれど)が
たくさんあるので、先生の指使いを教わる。
先生の楽譜で弾いてみると、かなり違う箇所がありました。
とりあえず1楽章最後まで辿り着きました。
この曲は本当に楽しいです。
ブラームスの後なので、余計開放感があるのかも知れません。
まずは音を正しく並べて正確に弾けるように
そして、音楽をどういう風に作っていくか考えて
テンポを上げていく。 というような目標を立ててみました。
重音のところが大変だけれど、なんとか攻略してみせるぞ~~。
あ、それからチェロオケの本番が近づいてきているのですが
演奏するホルベルク組曲で、3soloがありその部分の
低音を担当する事になったのですが、これがまた
地味に嫌な感じです。
私の音程が全て・・・なのでガンバリマス。
10月、11月に本番各1、12月に2つ。
12月は第九とベト1とブラ1という超豪華な曲ばかり。
大丈夫なんだろうかワタシ・・・。
↓ぽちっと応援してもらえると嬉しいです♪
PR
すっかりブログ更新サボり気味です・・・。
先週のVnオケ練は弦セクションの練習でした。
ブラームス交響曲1番の3楽章を全然合奏していないので
3楽章と4楽章をトレーナーの先生にみていただきました。
ボーイングや、弾き方の統一などなど
やらなくてはいけない事がたくさん!!!
3連休の真ん中の日だったので、出席人数が
少なかったのが少々残念でした・・・。
25日土曜日は本番指揮者指導のVnオケ合奏。
ベートーヴェン、ブラームス共に4楽章のみ。
ベートーヴェンは、少しテンポゆっくりで合奏。
1stVnはフェルマータの後の入り方や、cresc.の
持っていきかた、その後のpになる感じを練習。
基本的に、楽譜に書いてあることを忠実に表現することを
求められる練習でした。
sfの弾き方や、ffになった時に圧力を逃さないように
音を保つ事など。
特にfからffになる時の音量の変化(というかオケの音の厚み かな)
がもっと増すようにしたいようでした。
fで全開にしていると足りません!
ベートーヴェンは、ちょっとした仕掛け(急にpとか)や
遊び(和音の変化)などもあるので注意しなくてはいけません。
弓のコントロールや音程、そして音量に関しては
自分の中できちんと設定をしておかないとなかなか楽譜通りには弾けません。
ムズカシイなぁ~~。
ブラームス。
pizz.は今までの合奏でも、ずれないんだよね。と
もしかして褒められた?!?!
でも、大体こんなもんかな。と慣れてくると指揮を見なくなったり
予想で音を出したりしてしまうので(そしてずれる)、やっぱり
集中力と緊張感は保たないと!!
その後、Aからのテンポがどんどん前に進みます。
1stVnと2ndVnの掛け合いになる前の小節ではかなり。
掛け合い部分では落ち着いてテンポキープという感じ。
ここが合奏練習に出ていない人は落ちるだろうなぁ。
Bからの12連符(6連符)の所、急いで弾きすぎて
最後に数が足りなくなって「あれ?」と弓が止まったり
刻みの動きが一定でなくなってしまうと良くない。
正しく数を入れてください。とのことでした。
でも、うっかり数が合わなくなってしまったら、周りの弓の動きに同化して
指揮者にばれないようにすれば・・・。(内緒)
えーと、・・・本当は、ホルンのソロが始まったところで
どの位の速さで弾けば良いか、1章節分頭の中で練習できるので
そこで確認をするのが良いと思います。
ティンパニも同じ数打ってくれているし。
62小節アウフタクトからお待ちかねのあのメロディーです。
(Cbさんに羨ましがられた)
フレーズを長く歌うのかと質問したら、ソノーレで、と。
1音ずつを歌ってその1つずつの音を並べていく感じで。
要は、山を作らない(頂点の目標を作らない)歌い方という事です。
フレーズはやっぱり長く感じないと駄目かな。
8小節間を↑このように弾いて、その後はespress.です。
ここからは目標地点を持って歌う。
簡単に言うと、最初は淡々と、そして盛り上げていくという感じでしょうか。
Dのanimatoからは、オケの反応が良くなったからか
今までよりはテンポを上げるのが控えめになったようです。
この辺りからは音程がメチャメチャでした(ワタシが)・・・練習しよう・・・。
118小節から、私の大好きな所♪ブラ1の中で一番好きなメロディ♪
ここはかなり歌いこんで良いと思われる棒でした。
cresc.しっかり、そして盛り上げたところでpに落ちる。
この感じ、綺麗に出来たらゾクゾクしてしまう!!!
279小節からのリズム、頭の休符をしっかり感じすぎて
遅く重くなっていかないように。
思っているよりも、前に進む感じで良さそうです。
391小節前から加速はしていきますが、ここに入ったら
結構テンポが速いっっっ!!
指揮をしっかり見ないと迷子になってしまいます。
417小節アウフタクトからの3連符に入る所も鬼門です。
416小節で次のテンポになるのかな・・・。
ここから結構速いです。1stVnはこの位が楽しいですが・・・。
446小節までテンポ変わらず、 447小節からmeno mosso。
ここがなかなか指揮を見れず、意地悪をされました。
次の小節を振っていないのに入る人続出。
私はもちろん止まりました!!(威張)
最後の音、「ダウンアップね」と指揮者に聞かれました。
せんせーーーその質問3回目です。
スコアに書いておいて下さい!!!
というか、この質問はなんだろう?
もっと返せという事なのか???
そしてレッスンへ向けてのチェロ練習!
練習曲は100番から弾くと調子が悪いので83番から。
練習すればするほど課題が見えてくる・・・。
音はセパレートで弾くのか、レガートっぽくするのか
軽やかにするのかねっとり弾くのか・・・。
弓中から元の半分で弾くと書いてあるから
弓の弾力を使って楽しげに弾くのかなぁ・・・。
100番は逆に弓中から先の半分を使って弾く。
この曲もスタッカートに悩みます。
そして音程も難しい。弓を使う配分も・・・。
気をつけないとどんどん加速してしまい自分でクビをしめています。
バッハは少しずつ弾きやすくなってきた♪(自分比)
重音で力んでしまっていたのが、少しずつ右手のコントロールまで
気をまわす余裕が出てきました。
とにかく弾き込む!
サン=サーンスの譜読みは1楽章の難しい重音連続の箇所のある
ページを抜かせば、なんとなく出来たかな。
まだ読み込んでいくと色々な事が見えてくると思いますが
まずは楽譜通りの音を楽譜の指示通りに音にするところから
しっかり練習しなくては。この曲かなり楽しいです♪
さて、チェロ練習しなくちゃ。
あーなんだか凄い時間になっている・・・。
↓ぽちっと応援してもらえると嬉しいです♪
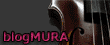

先週のVnオケ練は弦セクションの練習でした。
ブラームス交響曲1番の3楽章を全然合奏していないので
3楽章と4楽章をトレーナーの先生にみていただきました。
ボーイングや、弾き方の統一などなど
やらなくてはいけない事がたくさん!!!
3連休の真ん中の日だったので、出席人数が
少なかったのが少々残念でした・・・。
25日土曜日は本番指揮者指導のVnオケ合奏。
ベートーヴェン、ブラームス共に4楽章のみ。
ベートーヴェンは、少しテンポゆっくりで合奏。
1stVnはフェルマータの後の入り方や、cresc.の
持っていきかた、その後のpになる感じを練習。
基本的に、楽譜に書いてあることを忠実に表現することを
求められる練習でした。
sfの弾き方や、ffになった時に圧力を逃さないように
音を保つ事など。
特にfからffになる時の音量の変化(というかオケの音の厚み かな)
がもっと増すようにしたいようでした。
fで全開にしていると足りません!
ベートーヴェンは、ちょっとした仕掛け(急にpとか)や
遊び(和音の変化)などもあるので注意しなくてはいけません。
弓のコントロールや音程、そして音量に関しては
自分の中できちんと設定をしておかないとなかなか楽譜通りには弾けません。
ムズカシイなぁ~~。
ブラームス。
pizz.は今までの合奏でも、ずれないんだよね。と
もしかして褒められた?!?!
でも、大体こんなもんかな。と慣れてくると指揮を見なくなったり
予想で音を出したりしてしまうので(そしてずれる)、やっぱり
集中力と緊張感は保たないと!!
その後、Aからのテンポがどんどん前に進みます。
1stVnと2ndVnの掛け合いになる前の小節ではかなり。
掛け合い部分では落ち着いてテンポキープという感じ。
ここが合奏練習に出ていない人は落ちるだろうなぁ。
Bからの12連符(6連符)の所、急いで弾きすぎて
最後に数が足りなくなって「あれ?」と弓が止まったり
刻みの動きが一定でなくなってしまうと良くない。
正しく数を入れてください。とのことでした。
でも、うっかり数が合わなくなってしまったら、周りの弓の動きに同化して
指揮者にばれないようにすれば・・・。(内緒)
えーと、・・・本当は、ホルンのソロが始まったところで
どの位の速さで弾けば良いか、1章節分頭の中で練習できるので
そこで確認をするのが良いと思います。
ティンパニも同じ数打ってくれているし。
62小節アウフタクトからお待ちかねのあのメロディーです。
(Cbさんに羨ましがられた)
フレーズを長く歌うのかと質問したら、ソノーレで、と。
1音ずつを歌ってその1つずつの音を並べていく感じで。
要は、山を作らない(頂点の目標を作らない)歌い方という事です。
フレーズはやっぱり長く感じないと駄目かな。
8小節間を↑このように弾いて、その後はespress.です。
ここからは目標地点を持って歌う。
簡単に言うと、最初は淡々と、そして盛り上げていくという感じでしょうか。
Dのanimatoからは、オケの反応が良くなったからか
今までよりはテンポを上げるのが控えめになったようです。
この辺りからは音程がメチャメチャでした(ワタシが)・・・練習しよう・・・。
118小節から、私の大好きな所♪ブラ1の中で一番好きなメロディ♪
ここはかなり歌いこんで良いと思われる棒でした。
cresc.しっかり、そして盛り上げたところでpに落ちる。
この感じ、綺麗に出来たらゾクゾクしてしまう!!!
279小節からのリズム、頭の休符をしっかり感じすぎて
遅く重くなっていかないように。
思っているよりも、前に進む感じで良さそうです。
391小節前から加速はしていきますが、ここに入ったら
結構テンポが速いっっっ!!
指揮をしっかり見ないと迷子になってしまいます。
417小節アウフタクトからの3連符に入る所も鬼門です。
416小節で次のテンポになるのかな・・・。
ここから結構速いです。1stVnはこの位が楽しいですが・・・。
446小節までテンポ変わらず、 447小節からmeno mosso。
ここがなかなか指揮を見れず、意地悪をされました。

次の小節を振っていないのに入る人続出。
私はもちろん止まりました!!(威張)
最後の音、「ダウンアップね」と指揮者に聞かれました。
せんせーーーその質問3回目です。
スコアに書いておいて下さい!!!

というか、この質問はなんだろう?
もっと返せという事なのか???
そしてレッスンへ向けてのチェロ練習!
練習曲は100番から弾くと調子が悪いので83番から。
練習すればするほど課題が見えてくる・・・。
音はセパレートで弾くのか、レガートっぽくするのか
軽やかにするのかねっとり弾くのか・・・。
弓中から元の半分で弾くと書いてあるから
弓の弾力を使って楽しげに弾くのかなぁ・・・。
100番は逆に弓中から先の半分を使って弾く。
この曲もスタッカートに悩みます。
そして音程も難しい。弓を使う配分も・・・。
気をつけないとどんどん加速してしまい自分でクビをしめています。
バッハは少しずつ弾きやすくなってきた♪(自分比)
重音で力んでしまっていたのが、少しずつ右手のコントロールまで
気をまわす余裕が出てきました。
とにかく弾き込む!
サン=サーンスの譜読みは1楽章の難しい重音連続の箇所のある
ページを抜かせば、なんとなく出来たかな。
まだ読み込んでいくと色々な事が見えてくると思いますが
まずは楽譜通りの音を楽譜の指示通りに音にするところから
しっかり練習しなくては。この曲かなり楽しいです♪
さて、チェロ練習しなくちゃ。
あーなんだか凄い時間になっている・・・。
↓ぽちっと応援してもらえると嬉しいです♪
チェロのレッスンまで2週間切りました。
練習曲は
Alwin Schroeder 170 Foundation Studies for Violoncello Volume 2
から、100番、83番。
100番は大分前に宿題になっていたし、83番は結構好きな感じで
弾きやすいので、ついもう1曲手を出してしまっているのが86番。
100番と86番はとってもムズカシイ!!
100番は後半に出てくる5つスラーの後の1つのスタッカートで
弓の配分を調節するのが今一だし、ボーイングがたまに逆になったりしています。
86番はまだ譜読み段階で、最後まで音を読むので精一杯。
レガートに弾く事や、音程やなどにもっと気を使えるようにならないと。
そして、48小節でポジションが上がるところ、ここはどうしたら良い???
レッスンで質問するのを忘れないように☆印を書いておきました。
バッハの無伴奏チェロ組曲2番で宿題になっているのは
メヌエット1,2とジーグ。
メヌエット1の方は、重音でまず難易度がガツンと高いのですが
これに気をとられてメロディーが歌えていなかったり
伴奏になる音の横のつながりが見えなかったりしています。
ピアノで弾くイメージだと、音楽が良く見えてくるのですが
チェロで音を出していくと弾く事に必死になってしまいます。
左手をしっかり押さえる、というのが必死で押さえる、になってしまい
右手も左手につられて力む、という悪循環。
もっとゆっくりひとつひとつの音を丁寧に感じながら
弾く事に余裕が持てるテンポで練習をするようにしてみました。
C線からA線への移弦の所や、ボーイングの切れ目で
フレーズもブツッとならないように注意してみています。
練習を開始した頃は、重音を押さえるのがとっても大変でした。
今でも大変は大変ですが少しずつ余裕は出てきていると思います。
何気なく弾けるようになりたいけれど・・・まだまだ先かな。
2番のジーグは大好きです。
曲も大体イメージが湧いていて、あとは弾き慣れていけば!と
思っていますが、どうかなぁ。
3拍目の音の方向性、和音の変化、2声になる部分の意識など
気をつけてみています。
あ、1箇所どうしてもしっくり来ない所があるんでした。
くり返し記号9小節前のDE(重音)四分音符からGis八分音符
次の小節のCEA(重音)という所です。DEとGisの間で小ブレスして
1指でGisを弾いていた所から1ポジCEAに移動する左手の
動きが上手くいきません。
Gisでたっぷり時間を使って(ritという意味ではなく)、次の3和音の用意を
するのだろうなとは思うのですが・・・チェロはこういう手の移動が
遠いので本当に大変ですよね・・・。
バッハは2番が終わったら3番をやりたい!と思っているけれど
残すこの2曲(3曲?)しっかり練習して、音の羅列ではなく
きちんと弾けるように頑張ります♪
それから、来年の発表会で出来たら良いな・・・の曲。
サン=サーンスのチェロコンを譜読みしています。
楽しくて、ついどんどん読んで、最後まで・・・。
さすがに3楽章は激ムズですねっ。

この曲は、今年の発表会で課題として残っている
音色の改善をきちんとしていかないと、曲にならないので
ヴィブラートの研究をしなくてはいけないです。
素敵なヴィブラート、耳で聴こえる部分では
1音にかけている回数とか、音色とか理解は出来るのですが
実際体でコントロールする部分で、どういう仕組みになっているのか
やっぱりまだ理解が全然足りないです。
まず、ノンヴィブラートで良い音でロングトーン。
これにゆっくり柔らかくヴィブラートをかけていく。
低いポジションではそこそこですが、ポジションが
上がるにつれ、3の指が特に難しくなってきます。
何が変化してしまっているのか、ずっとずっと考えました。
やっぱり、ポジションが上がって左手の形が変わると
指板に対する押さえる力の働きの方向が変わって
手首や上腕が強張ってしまうみたいです。
強張ると、結局そこから先でしか振れないわけなので
ちりめんになってしまい、硬い音にもなってしまうような。
苦手なポジションや指を使ってたくさん弾いて
少しずつ慣れていくしかないのかな。
音色と音程。どんどん磨いていきたいです。
発表会の講師演奏の時の先生の音色を目標に!(理想は高く!!!)
↓ぽちっと応援してもらえると嬉しいです♪
